休日にタピオカをしばく四十路の元404の話です
志摩一未のもとに、かつての相棒である伊吹藍から電話が来たのは、ある初夏の朝のことだった。
「なあ志摩ちゃん、タピオカ飲み行かね?」
「タピオカ?」
「そそ、タピオカ〜。なんか今すごい流行ってんじゃん?」
世は空前の……ではなく、二〇一九年についでかれこれ四度目になろうかというタピオカブームだった。いつか見た風景と同じように、しかしあの頃とは異なるファッションに身を包んだ若者が、こぞってタピオカドリンクを持ち、今日も街を闊歩している。
日に日にタピオカドリンク専門店が増える中、果たして前回のブームのあとにどれだけの店舗が潰れただろうかと、志摩は考える。今まさに増えている店も、これからどうなるのか。前回は新型ウイルスの流行もあったが、それがなくとも多くは店を畳むだろう。そしてその場所にまたあたらしい流行の店ができる。その繰り返し。街の新陳代謝は今日も活発だ。良くも悪くも。
「いつなら予定合いそう? この機を逃さずタピろうぜ」
「今日」
「え?」
「今日なら空いてる。電話かけてきたってことはお前も今日休みだろ」
かくして寝て過ごすはずだった休日は、伊吹と“タピる”ことになった。
404バディを解散してからも、彼らの縁が切れることはなかった。忙しい中でも誘い合っては飲みに行ったし、都合がつけば陣馬や九重も一緒だった。ゆたかに請われて家族のように遊びに行くこともあったが、そのゆたかも既にハイティーンだ。時の流れは早い。特におとなから見るこどもの時間は。
待ち合わせ場所に志摩が赴くと、伊吹は既にそこにいた。午前十時。決して涼しいとは言えないが、まだ耐え難いような暑さではない。
ここ数年、日本の夏は驚くほど人間に厳しい。それでも伊吹は変わらず長袖で、志摩はひそかに感心する。以前、伊吹は冬のほうが好きだと語っていた。着込むのが楽しいからと。志摩には伊吹のファッションはよくわからないが、そういうものか、と思う。ちなみに志摩は過ごしやすければなんだっていい。夏は暑いし冬は寒い。
「よっ」
「おう」
いざ顔を合わせると、なんで貴重な休日に四十路のおっさんふたりでタピオカなんか飲まなきゃならないんだ? という思いが湧いてきた。だが志摩は伊吹の誘いを都合以外で断ったことがないし、おそらくそれは伊吹も同じだった。断ったとしても必ずどこかで埋め合わせをする。……それに、もしもタピオカが口実で、大切な要件がほかにあったらどうするんだ。志摩は思う。伊吹はとうに仕事上の相棒ではないが、それでもやはり相棒だった。
「で、どうしてタピオカ?」
「え? 飲みたかったから。てかタピオカ飲みたい以外のタピオカ飲む理由とかある?」
伊吹があんまり軽く言うので、志摩も軽い溜息で返す。この男はそういうやつだ。わかりきっていたことだが、溜息くらいは許されたい。
「ほかにもあるだろ、なんか。流行りに乗りたいとか、写真を撮りたいとか」
「最近またなんかあたらしいのが流行ってるよね〜」
写真を撮って、今それがどのサービスにアップロードされているのか、志摩はよく知らない。出会った頃ですらインターネットに疎かったのに、昨今の流行り廃りを知るわけもない。ひょっとすると、写真を撮るというのもとうにおじさんの発想で、とっくにそれに代わる何かが台頭しているのかもしれない。
思考が逸れた。伊吹と話すとずっとそうだ。十年あまり、ずっと。逸れ放題でいやに豊かな寄り道が、振り返れば無数にある。
「……タピりたい理由はそうとして、じゃあわざわざ俺とタピりたい理由はなんだ?」
そう言うと、伊吹はチェシャ猫のように目を細めて心底おかしそうに笑った。目尻に寄る皺は出会った頃よりも深い。
「タピるって……志摩の口から……」
「言い出したのはお前……もういい、で、なんなんだ」
さっきまで肩を震わせていた伊吹が、不意に静かに志摩の顔をまっすぐ見る。そしてまた笑う。
「いやだってさあ、前回のタピオカブームが、ちょうど俺たちが四機捜でバディ組んだ頃じゃん? なーんか懐かしくなっちゃってさあ。密行中に並ぶわけにもいかないし、あの頃わざわざ休みの日に会ったりしなかったじゃん」
そもそも密行中なんてカップの飲み物すら買わないのに――初日に伊吹は買っていたが――タピオカなんて論外だろう。志摩はこれまでタピオカドリンクを飲んだことすらない。
「だからさ、志摩と飲みたかったの。タピオカ」
そう言われてしまえば、志摩だって懐かしい。年月が経つほどに、つい回顧することが増える。自分がそういう歳の重ね方をすることが、志摩には意外だった。それはしばしば面倒で、基本的には悪くなかった。いろいろなことがどうでもよくなる瞬間が今でもまったくないわけではないが、それでも志摩は、もう間違えたくなかった。
「一番ちいさいサイズ、甘さ控えめでください。あ、氷……氷もすくなめで」
開店直後だったためか、思っていたほどの混雑はなかった。それでも場違いだな、と志摩は思うが、伊吹はまったく気にしていない。彼の頼んだレギュラーサイズは、志摩にはとても飲みきれる気がしなかった。
「志摩ちゃんダイエット中みたいな頼み方するね」
「お前はこの歳になってよくそれだけ飲めるな」
レシート片手にできあがるのを待ちながら、なんとなく伊吹を見上げる。若々しいな、なんて浮かんだ感想にすこし笑ってしまって、また前を見た。高齢化に拍車のかかるこの国では四十路なんてまだまだこれからという扱いを受けるが、自分自身がそう思えるかは別だ。健康診断に怯えるようになって早幾年。すくなくとも肉体は、まだゆるやかでも坂道を順調に下っている。
商品を受け取って店を出て、タピオカ片手に散策する。ひとくち啜り、タピオカを咀嚼し、飲み下す。黒糖が甘い。伊吹がいなければ飲まないまま生涯を終えていただろう。
「これ昼もう食えねえな」
「えっ嘘、俺ぜんぜんラーメンでも行けるけど」
「行くならひとりで行け」
「何なら食える? やっぱうどん?」
「うどん……ならまあ……」
「じゃ、昼はうどんだなー」
タピオカを飲んでハイさよならとは思っていなかったが、自然に昼食を共にすることになっていた。このまま夜まで一緒なのだろう。こういう休日は自分には似合わないな、と自嘲しかけてやめた。生きていれば、こういう日もある。そしてそれは存外楽しい。
伊吹がたまに訪れるうどん屋があるというので、タピを吸い吸いそこに向かってのんびり歩いた。すこしでも焦ったり走ったりすれば汗ばんでしまうだろうという微妙な陽気で、手元のつめたいカップがすこしだけありがたい。飲むには重いが。
「伊吹、説明するのうまくなったな」
「え?」
「どうして俺とタピオカを飲みたかったのか、さっきかなりスムーズに説明してた」
不意に生まれた会話の隙間に、志摩は今朝のちいさな疑問を差し込んだ。半年と間を置かずに会っているとはいえ、一時期のように二十四時間を共にしたりはしていない。伊吹には伊吹の時間が流れている。志摩の知らないところで。
「あー、それはねー、もしかしたら志摩ちゃんのおかげかも」
「は?」
「志摩と組んでた頃は、志摩が俺の話ちゃんと聞いてくれてたじゃん。だから異動してからは、俺のー、なんつーの感じ? ひらめき? を誰かに伝えるときに、俺の心の中の志摩に、どうしてそう思うんだ? って言ってもらってた」
「それ俺の真似か? 似てねー」
「うっせ。……で、なんでだー? って考えて、これかー? って思ったことを伝えるようにしてる。その成果が出ちゃったな〜」
「やっぱ説明下手だわ」
「ええ嘘!? 俺今超真面目に説明したじゃん!」
志摩は何かをごまかすようにストローに口をつけた。伊吹の中に自分が息づいている。それは伊吹と出会った志摩の、人生の選択の結果にほかならない。志摩と伊吹が関わり合って生きてきた証だった。
だって、志摩の中でも伊吹はたしかに息づいていた。迷うとき、ためらうとき、志摩は心の中の伊吹に問いかける。どうすればいい。どうすれば間違わない。志摩は自分の良心のような何かが儚いことを知っている。正しさが弱く虚しいことを知っている。だから、心の中の伊吹藍に問うのだ。どうすればいい。
だが、それを口にするのは今ではないと思った。こんな弾み、こんな流れの中ではなく、もっとちゃんと、改めて。これではまるでプロポーズのようだと思い至り苦笑した。いつか定年まで勤め上げられたとしたら、そのとき伊吹に感謝と共に伝えよう。ここまで来られたのはお前のおかげだと。そう思った。
伊吹とはあまり近況報告をしない。するにはするが、会えばつい先日振りかのようにどうでもいい話を重ねてしまうため、長く花の咲く話題ではない。だから、九重が見合いを勧められているという話が出たのも随分話し込んでからだった。
きゅうちゃんお見合いさせられそうらしいよ。させられそうらしい、って曖昧な日本語だな。お見合いってぜんぜん想像つかない、つか何すんの? ご趣味の話とか? 今日びお見合いなんて逆にすごいけど、気は進まないだろうな。
「そういえば、伊吹に言ってないことがあった」
志摩がそう切り出したのは、病院の前を通りがかったからだった。
「えっ何、実は志摩もう結婚してたとか?」
「ちがう。桔梗さんじゃあるまいし」
「そういや志摩、旦那さんのお店も行ったことないんだっけ」
「いつの間にか産休とっててそこではじめて知った」
「嘘、し、志摩、志摩ちゃん、そんな」
「笑うな」
笑うなと言いつつ志摩も笑った。流石にこれほど時が経つと自分でも笑えるし、いっそ笑ってくれたほうが楽なものだ。過去のすべてがそう軽やかになるわけではないが、そういう一頁があるだけ有り難いのかもしれない。
「いやそうじゃない! そうじゃなくて、志摩の暴露の話! 何!」
「ああいや、……俺のスマホの緊急連絡先に伊吹が入ってるって話」
え、と伊吹は驚いたように固まった。志摩はちらと横目でそれを捉えたが、足を止めはしなかったので、一瞬のことだった。伊吹はすぐに歩きはじめる。志摩と並んで。
「もしものことがあったとき、最悪お前になんの連絡も行かないこともあると考えると……俺が嫌だったから」
植え込みに気の早い蝉がいるらしく、ぎー、ぎー、と鳴いていた。蝉が鳴くと思い出す。香坂の死んだ夏。蒲郡を逮捕した夏。伊吹は思い出しているのだろうか。わからない。志摩と伊吹はちがう人間だから。それでも志摩は、伊吹の夏がすこしでもやわらかいものだといいと思う。たとえ太陽が年々過酷に照りつけてゆくのだとしても。
考えなかったわけではない。恩人の認知症を知り一緒に暮らそうと提案する伊吹が、病院から連絡を受けてさえいれば飛んでいかなかったはずがないのだ。見舞いどころか着替えの用意も家の管理もなんだって進んでしただろう。もしもそうだったなら、何かが変わっていたかもしれない。だが時は戻らない。
伊吹には長生きしろよと言いながら、自分が伊吹を置いてゆく可能性を考えたとき、すくなくともそれが、引きちぎられるようなものでないといいと思った。だから、それは自然なことだった。
そうすることで、間に合う何かがあるかもしれないから。
「志摩ちゃん、それ、俺もしていい?」
複雑な声音で伊吹は言った。おとなのようなこどものような、うれしいようなせつないような、さみしいようなまったくさみしくないような、不思議な声だった。伊吹藍という人間の深さを志摩は想った。この苦い世界でそれでも生きてゆかねばならないというのなら、俺のそばに伊吹がいてよかった。……俺はラッキーだったなあ。いつか伊吹がそう言っていた。俺の僥倖はお前だよ。騒々しくも心地よく、しばしば痛みをもたらす、僥倖。
「伊吹のしたいようにすればいい」
「やった。俺もしよ〜。てかお互いこれが役に立つ羽目にならないようにがんばろうね」
「そうだなあ」
病院も、蝉も、既に後方に遠ざかっていた。
いつの間にか太陽の位置が高くなってきていた。
手にしたタピオカドリンクを三分の二ほど飲んだ伊吹が、ごめん、と不意に言って足を止めた。なんだ、と振り返ると、何やら神妙な顔つきでカップを見つめている。
「ラーメンは盛った。いや食えなくはないけど、余裕ではない」
それがほんとうに深刻そうな表情だったので、志摩は堪えきれずに笑った。端からそんなに堪える気もなかった。だって伊吹相手に。
伊吹は笑う志摩をたしなめもせずにひたすら悔しがっていた。うわ認めたくねえー、ジョギング増やそうかな、こういうのってどうしたらいいの。飯? 酒?
「お前もちゃんと歳とってんだなあ」
「うわムカつくー。言っとくけどひとくちで悟った志摩には勝ってるからね」
「それには返す言葉もないな」
ず、とまたひとくちタピオカドリンクを飲んだ伊吹は、けれどさっきまでの悔しさを吹っ切ったようにニカッと笑った。
「ま、でもさー。また次タピオカが流行る頃にはスモールをはんぶんこすることになっててもさ、そんときもふたりで飲もうぜ」
「……了解、相棒」
タピオカドリンクは底をつき、うどん屋はもうすぐそこだった。

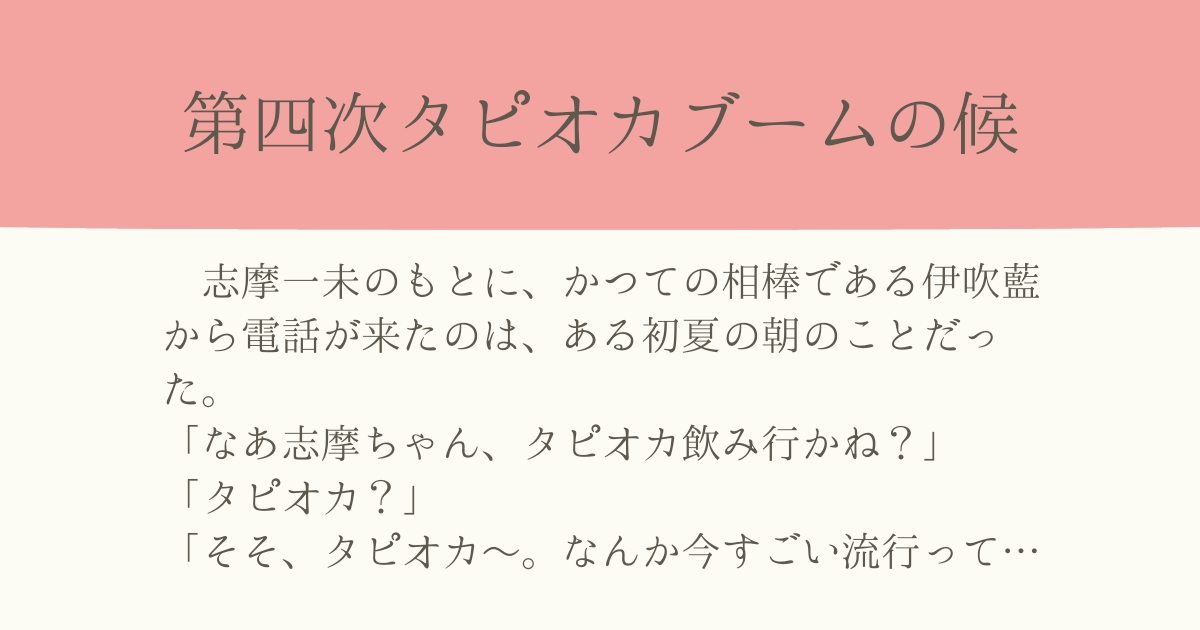
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます