最終話後の十月頃、したたかに酔って同衾するも特に何も起こらない404の朝の話です
目が覚めると、ふたりだった。
昨夜の志摩一未は深酒をした。酒を飲んで、気分がよくて、酒が進んで、そうして眠った。隣を見る。――伊吹藍。
ほんの一瞬、まさかな、と考える。だが、志摩は酒で記憶を飛ばせる性質ではなかった。服だって上下ともに身に着けている。終電後に走る貨物列車の音を並んで聞き、下がりはじめた秋の気温と平素の仮眠の慣れもあり、同じベッドで眠っただけ。それだけだった。
医師からアルコールの摂取を解禁されて数日。昨夜はいつもの店で飲んで、なんとなく飲み足りなくて、どちらからともなく二軒目を切り出した。だがいい店が見つからず、自宅に誘ったのは志摩だった。志摩だけが伊吹の部屋を知っているのはフェアではない気がしていた。
――記憶のリプレイは熱の身じろぎで停止した。隣で眠る伊吹のまぶたが震える。ややあってそれが開き、志摩と合わせた目線が泳ぐ。どうやら彼も、刹那の“まさか”の渦中らしい。
「“まさか”はないぞ」
「だよね!? っぶね~一瞬マジでびびった~」
「寝起き一発目の声量じゃねえ……」
ましてやあれだけ飲んだ翌朝のそれではない。言うやいなやベッドから降りた伊吹は、ぐ、と伸びをして、それですっかり目覚めたようだった。
「志摩ちゃん今日の予定は? 俺何時までに出たほうがいいとかある?」
「いや、特には。洗面所とか好きに使えよ。……あ、シャワー浴びるか。それも適当に」
うーい、さんきゅー。間延びした声が遠ざかるのを聞きながらひとつあくびをして、志摩もベッドから出た。シャワー借りんねと壁越しに聞こえたが、声を張り上げるのは億劫で特に返事はしなかった。志摩は伊吹ではないから。
くぐもった水音を聞きながら、とりあえず飯、と考える。密行中の朝食――というよりは朝頃に胃に入れるもの――はおにぎりだったりパンだったりとふたりとも気まぐれだ。ハンバーガーは食べようとするたびになぜか入電があるので、いつの間にかふたりとも買わなくなった。伊吹は出されたものに文句をつけるような男でもない。食パンがあった気がするのでそれでいいだろう。
顔を洗うついでに脱衣所にタオルを置き、コーヒーでも淹れようと湯を沸かしていると、浴室の戸が開く音がして、ややあって伊吹が顔を出した。早い。
「シャワーありがとうございました。おはようございます」
「なんで敬語」
「や、挨拶って大事じゃん?」
そういえば初日も挨拶だけはきちんとしていたのを思い出す。そして挨拶を大事にしろと、彼に教えたひとを想う。はたしてそれは、彼が師匠と呼び慕うひとだろうか。なんにせよ、わざわざ尋ねることでもなかった。
「……どういたしまして、おはようございます」
「どもども~」
「食パン焼くけど、お前は?」
「何枚のやつ?」
「四枚切り」
「じゃ一枚かな~。いいの? もらっちゃって」
トーストを二枚セット。どのみち三枚以上は焼けないので、あとで考えればいいと思いつつ喋る。
「足りるのかそれで……あ」
「ん?」
「……プチトマト」
プチトマト、と伊吹が復唱したのがなんとなく愉快で、志摩はかすかに笑った。カーテンと窓を開け、スリッパを突っかけてベランダに出る。その背中を伊吹が追う。その様子にまだ幼かった頃のきょうだいを思い出し、また笑う。
「ほんとにプチトマトだ。えっ志摩プチトマト育ててんの?」
ベランダに鎮座しているのは、プチトマトの苗だった。大きめのプランター、たっぷりの土、しっかりとした支柱、剪定された青い葉に、腐り落ちる寸前の熟れきった赤い実。お手本のような世界にひとつのプチトマトは、それなりに手を掛けて育てられているらしかった。
「もっと早くに最後の収穫だったのに、最近忙しかったろ。なんならいくつか持って帰るか」
「えっやった! てかこれ何」
「だからプチトマト」
「いやそうじゃなくて、なんで? なんで志摩プチトマト育ててんの? なんか意外」
「相棒への理解が足りてなかったな。残念」
片膝を立ててしゃがみこんだ志摩は、苗の中でもとりわけ赤い実を撫でた。よく熟れたそれは力を込めずとも簡単に茎から離れ、それをやわらかく受け止める。やはりもうすこし早く収穫してやるべきだった。志摩は悔やんだが、伊吹が楽しそうなので、まあいいか、と思い直した。
俺もやってみていい? 伊吹が言うので断る理由もなく快諾し、志摩はその様子を眺めた。立ち上がり、スリッパを右足だけ伊吹に寄越す。床に左足を残して器用に腰を下ろした伊吹は、やさしい手つきでプチトマトにふれた。てのひらに収まったそれに視線を落として、口を開く。
「意外だったけど、似合ってる。プチトマト育てる志摩」
志摩は虚を突かれた思いで伊吹を見た。野菜を栽培し、収穫し、食べる。そういう営みを似合うと評されるのは、どこかこそばゆいものがあった。どうだか、と言いかけて、やめる。
「……元カノ」
なんでなんでと問われる限りは何も話す気はなかったが、不思議と話してもいいと思えた。自分がこんなにも素直な被疑者であることも、伊吹が図らずも優秀な刑事であることも、なんだかおかしかった。
「元カノ!? 志摩ちゃんの!?」
「わかりやすく色めき立つな。……栽培キット持ってきて、置いたまま別れて、それからもなんとなく毎年」
「え、これどう見ても栽培キットじゃないけど。めちゃくちゃマジのやつじゃん」
「もう今あるのは全部自分で買ったのだな。どんどん凝っていって……」
免許試験場の頃はすることもなくて……捜査一課の頃は必ず枯らすくせになぜか毎年種は蒔いてて……この話は別にしなくてもいいか。本格的に育てはじめると夏が終わってもしばらくは実をつけるようになって……話そうとしたそのとき、トーストの焼き上がりを知らせる音が鳴り、志摩はスリッパを適当に脱いで部屋に上がった。湯はもう沸いていた。
「パンに塗るものとかないけど」
「ぜんぜんいいってマジでサンキュー」
いただきます。インスタントのコーヒー、何も塗らないトースト、ベランダで育てたプチトマト。プチトマトは育てるくせに、豆は挽かず、パンは焼いて素のまま。なんとなくちぐはぐに思えて、それを飾り立てせず伊吹と共有するのは、妙に恥ずかしかった。そんなことが、なぜか今更。
「もしこんなシーンがドラマであったら、ああこのふたりは昨夜お楽しみだったんだな、と思うだろうな」
「……キャッキャウフフなところはなくても?」
「そういうもんだろ。後朝ってやつ」
「きぬぎぬ?」
「キャッキャウフフの翌朝のこと」
「じゃ俺ら今キヌギヌモドキ?」
「それあれっぽい、なんだっけ、メフィストフェレスの」
「メケメケフェレット」
「それだ。……ふ、何もそれじゃない……」
「志摩たまにツボ浅いよね」
トーストはあっという間に胃袋に収まり、コーヒーを啜る。プチトマトはかなりやわらかく、それでもちゃんとおいしかった。間に合ってよかったと、志摩は思う。腐り落ちてしまう前に、収穫できてよかった。
「トマトうまっ。え、こんなうまいもんなの」
「去年のほうがよくできてた。最初の頃に比べたら今年もうまいけど」
「それもう農家になれんじゃない?」
農家。声に出た。あまりに突拍子もないその姿はうまく想像できなかった。定年退職したらうどん屋やれば? そう言われたことを思い出す。農家、うどん屋、ひとごろし。
昨夜、もしも伊吹と“まさか”があったら、いったいどうなっていただろう。それに思い至った瞬間、不思議な感覚があった。覗き込んだ万華鏡を回したときのような、開かれながら閉じている感覚。世界の見え方が変わるのに、同じ場所に立っている自分。そして変わらず目の前にいる伊吹藍。いくつもの分岐点。無数に存在する選ばなかった道と、これから選ぶかもしれない道。万華鏡の中の、農家、うどん屋、ひとごろし、“まさか”。
「刑事とどっちが大変なんだろうな」
何気なく迎えたこの朝は、たぶん貴重な朝だった。
「もし俺か志摩のどっちかがきゅるっとした女の子だったら、ウフフってたのかなー」
どきりとした。志摩はしばしば伊吹の勘に驚かされるが、伊吹は伊吹でこの状況に何か思うところがあるのだろう。そもそも“まさか”という発想が生まれる時点で、ふたりの距離は随分近い。
「だとしたらこの状況になってないだろ。……でも、たとえ俺がそのきゅるっとした子でも、ウフフはない」
「なんで言い切れんの」
「お前が伊吹だから。……伊吹は、取り返しのつかないことをする前に、ちゃんとそれを恐れて、ためらうことができる。だから、はずみでウフフはしない」
人生は選択の連続。吐き出した言葉は戻らない。喪った生命は還らない。“まさか”には関係を変質させるリスクがあり、だからこそ“まさか”なのだ。おしなべて人間は不可逆の時間を生きている。
伊吹は何かを堪えるような表情をしていた。なんとなく志摩はその内側を察して、だから何も言わずに片眉を上げた。お前ははずみでウフフはしないし、引き金に掛けた指だって外せる。外せるよ。伊吹。彼の見た夢の仔細は知らないが、おそらくはそういうことだった。自分のことを棚に上げて、けれど志摩は、伊吹にはそう思った。
皿の上にひとつ残ったプチトマトを、思い立って志摩は伊吹の口に押しつけた。伊吹は従順にくちびるを開き、咀嚼、嚥下する。あの夢の中では腐っていたはずの、今ここにあり、やがて彼の肉体になる、プチトマト。
「志摩さあ、俺のことだいすきだよね」
その言葉のトーンはすっかりさわやかで、たぶん、志摩は混ぜっ返してもよかった。だがそれをするのは、今このときばかりは不誠実に思えてならなかった。身勝手な自分を飼い慣らす。手放せはしなくても、せめて、つとめて。
「相棒への理解が深い」
それだけ言って、志摩は皿を手に立ち上がった。食事の次は皿洗いだから。志摩ちゃん! 懐くなじゃれるな。危ないだろ皿持って……交わす言葉の一つひとつが、大丈夫だった。きっととっくに大丈夫で、けれどそれを確認できたのは、よかった。
志摩はベランダに出て、ちいさなタッパーにプチトマトを入れる。今日明日で食べなければならないだろうから、もったいぶるようなものでもなかった。
「えっそんないいの。もう超~ありがとう」
「食いきれないから礼を言うのはこっち。助かる」
蓋を閉めて手渡したところで、伊吹が鞄を持ち歩かないのを思い出した。適当な紙袋を探し当て、それも渡す。こういうのは、それなりに長く暮らせば家のどこかしらにある。
「志摩ちゃんさあ、プチトマトの世話しながら元カノのこと思い出したりすんの?」
「いや、今日かなり久々に思い出した」
薄情だろうか。けれどほんとうのことだった。志摩は揶揄されるかと構えたが、伊吹は存外やわらかく言った。なんかいいな、それ。
「だってもうさー、そのプチトマトは志摩の一部じゃん。志摩の生活。なんかいいよなーそういうのって」
志摩は今朝の伊吹の挨拶を思い出した。それから昨夜のことも。殴ってごめんなさい。謝るのはこっちだろ。俺が悪かった、ごめん。
こどもみたいな痛み分けが、おとなに不要ということはない。おとなだって、水に流すなんて綺麗なことは、とても難しい。ハンプティ・ダンプティ。水が流すのは、むしろ、もっと。久住は沈黙をつらぬいている。
たとえ彼の恩人が取り返しのつかない罪を犯したのだとしても、今でも彼は挨拶を大事にしている。それは伊吹の美点だと、志摩は思う。ひとの人生は、そういうふうに形づくられ、続いてゆくものなのだろう。
「なあ伊吹」
「ん?」
「この街のどこにいても、俺は、ああ伊吹と走った街だ、ってふっと考えてる。街のあちこち、どこでも全部。……伊吹の大事な、伊吹の街だ、って」
玄関に座って靴を履く伊吹の背に、志摩はそう言った。伊吹がその足で追いかけたものの数々。守っていると言い切ることはとてもできない。それでも彼の一歩ごとに、この街は伊吹の街になる。これまでも、これからも、あるいは、もし伊吹がいなくなっても。志摩にとって伊吹は、欠かしようのないこの街の要素だった。
靴紐をキュ、と結んで立ち上がった伊吹が振り返る。穏やかで、どこか晴れやかな顔をしていた。
「俺らの街だもんな」
「そうだな」
万華鏡の中にはない、ここにしかない、機捜404の街。綺麗で猥雑で、誰かの帰る家があり、誰かがさまよっている。そういう場所が、志摩と伊吹の街だった。
重ねて礼を言う伊吹に、重ねて気にするなと言って、まだ午前も半ば。今日洗濯しないとやばいんだよね。あ、俺もだ。早起きできてよかったね。三文の得。それそれ。
……それじゃ、また明日。また明日。
伊吹の去った扉が閉まり、志摩はふと意味のないことに気がついた。
――“まさか”だったら、プチトマトのことなんてすっかり忘れて腐らせただろうな。
何も死ぬわけではないのだから、来年また育てればいい。けれど今年はもうだめだった。捉え方次第だなとひとりごちて、志摩は鍵を閉めた。洗濯をしたら、午後は散歩でもしようかという気分だった。

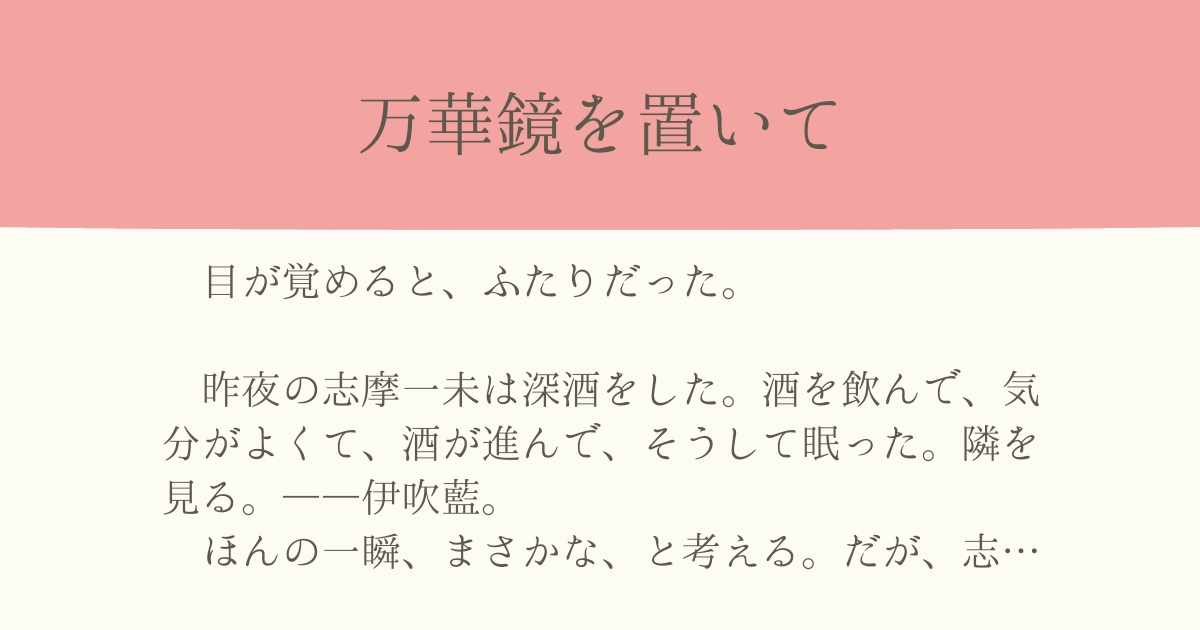
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます